いよいよ夏本番とも言えるくらいに暑さも本格化してきましたが、ここ数日は一変して過ごしやすい気候です。
週末の午後の練習なんかは16時開始にしていますが、その時間でも日光が照り付け、体への直接的なダメージを感じずにはいられません。
真夏ともなればこれがまたさらに激しさを増すわけで、息をするのも苦しい、そんな灼熱地獄が待ち受けているのですから、昨今言われる熱中症リスクには十分気を付けたいものですね。
実際に私もこの寒暖差に体がついていけず、昨晩発熱してしまいました。
これはいわゆるお疲れ熱だとも思いますが、無理は禁物だと自分に言い聞かせてます。
さて、いつもであれば週末の活動報告をさせてもらっていますが、今回は少し趣向を変えて発信させてもらいます。
素意や、素意や~
まずいつもこのブログをお読みいただいている方々、誠にありがとうございます。
いつも更新を楽しみにしていると聞くと、なんだか無性に頑張りたくなる一方で、このブログについて批判の声もいただきます。
もちろんここに書かれた内容については、キラキラとした青春の1ページとなる部活動という一面だけでなく、もっとドロドロとした言わばコンフリクトのようなことも現場では起こっています。
そして、ここに私が書く事柄についてもボート部を、そして自分をも良く見せようとする思いがあるのは事実であり、それをなんら否定するつもりはありません。
でもなぜ私がここにつらつらと今を伝える発信をしているかと言うと読み手となるターゲットを特に意識しているからです。
その読み手とは誰を指すか、それは部に関わるすべての方です。
たとえば、監督としてこう感じた、こう思っているというのを直接的に選手に伝えるより、このブログを通じて伝えていることも一つにはあります。
もちろん部の現状や頑張っている部員たちにフォーカスして、これを応援してくれる保護者の方々、支援してくれるOB,OGの方々へも伝えてもいます。
それは部に関わる方として関心を持ってくれているからこそ、こうしたメッセージや思いを発信しています。
そしてその読み手の方々も私自身への期待ではなく、ボート部やこの組織、そしてそこに集う学生らへの期待の表れであるからこそ、こうして気にかけてくれるのだとも思っています。
私たちはまだまだ未完成な組織であることは百も承知しております。
だからこそ、より良くするための選択と行動を常に考え、それぞれが選択し、行動していっているのだと思います。
時には間違いを犯したり、失敗をすることだってあります。
でも人も組織もこうして皆でともに創り上げていくものだと思っています。
主観的に見れば今の組織は組織として呈を成していないと批判的に映ることだって当然あることでしょう。
でもそれはその人自身の物差しで見ているからこそであり、言うならば「群盲、象をなでる」のことわざに似ている節もあります。
私の監督としてのスタンスについても部全体のことを考えて物事を判断しています。
個人や一部分だけを見て、そこに最適化した判断をすることは極力避けるようにしています。
なぜなら、そのような場合、どんな判断を行っても、必ず不満分子が出てくるからです。
人は他者評価より、自己評価の方が高い傾向にあるから仕方のないことかもしれません。
でもだからこそ、全体最適という視点で物事を判断するようにいつも心がけています。
それはある一時点での組織全体での最適というだけでなく、未来の組織まで含めた最適を考えてのものです。
その場合、「今」の人は損をして、「未来」の人は得することになりかねないので、「未来志向の判断」に不満を持つ人もいることでしょう。
それでもこのボート部を未来永劫続けていくことこそが使命であるからこそ、そのような考えを持ち合わせています。
私のこうした考えに基づくやり方を誰も望んでいないとあれば、それはすぐに身を引く覚悟もあります。
ただし、その批判をもってして、すべてを終えるかといえばそうもいきません。
希望に満ちた若者たちが集い、この場所で努力して自らを輝かせようとしているからです。
そしてまたその者たちを応援する人々の声も確実に私のもとへ届けられているからです。
先にも述べたように我々は未完成であり、このブログで書いたことが皆さんの目にどう映っているかは定かではありません。
ですが、希望に満ちた部員たちが輝こうと努力する姿は本物であり、それこそがこの部の究極の目的であるからこそ、その事実だけはしっかりと伝えていかねばならないのです。
だからこそ、彼ら、彼女らの頑張りを評価し、応援し続ける者の立場としてこれを止めることはできないのです。
最後にコーチ論についても少し述べておきます。
既に多くの方がご存じであるように、ティーチングとは多くの場合、上の者が下の者に対して行動を指示したり、ある課題に対する答えを与える意味として用いられます。
コーチングはその逆で、下の者が自ら答えを導きだしたり、課題解決の方法を見出していくことを「支援する」方法論です。
コミュニケーションの手段として、時にはティーチングが必要なときはそのように振る舞うことも当然ありますが、どちらかと言うとコーチングを用いることを常に意識しています。
私たちの指導の根底には、選手らができないことをできるようになることを「支援」したり、できることをより高いレベルでできるように「支援」することがあるからです。
試合で勝つことを目指すのもありますが、それはあくまでこれらを実践していく中での副産物です。
なぜならコーチがプレーヤーの有能さと人間性を直接的に向上させることは不可能であると言われているからです。(当然自身でもそう思っています)
有能さを向上させるのも、人間性を向上させるのも、直接的に行うのはプレーヤー本人にしかできないことです。
ですから我々はプレーヤーの環境の一部として間接的に影響を与えることはできても、直接的にプレーヤー自身を変えることはできないのです。
だからこそ、「支援」という言葉を使うことが適切だと言われる所以です。
コーチングを定義するとすれば、プレーヤーの目標達成に向け、プレーヤーの有能さと人間性を高めていく「支援」を行っていくプロセスを総称してコーチングと呼び、このプロセスを行う人をコーチと呼びます。
つまり私もまたコーチの一人なのです。
見方を変えれば、組織全体を管理しきれないことを放任主義だと罵られることもありますが、それはどこかまた別の組織と比較したり、別の立場と比較した視点ではないでしょうか。
高校の部活動と大学の部活動も運営主体や目的そのものが異なるわけで、当然組織としての在り方、作り方も異なるものなのです。
そして大学の部活動は部員らが主体的に作っていくこと、自律していくことにこそ、面白みがあり、得られるものもまた大きいのだと私は思います。
だからこそ、未完成であっても自らが作り上げていく気概がなければ何も変わりません。
自身がどんなに正しいと思い行動しても、相手に伝わらず変わらなければ何の意味もありません。
その伝え方、接し方すら年々難しさを増しています。
それでも私たち指導者はいつ何時だって、この支援するかたちを追求し、理想を追い求めてきました。
これからも変わることなく、歩み続けていくつもりです。
もし本当に私自身の存在が必要でなくなれば、また間違いだと説いてくれるのであれば、喜んで身を引くことでしょう。
この部の発展を誰より願うものとして。
素意や、素意や~
咲きほこる花は 散るからこそに美しい
散ったはなびらは 後は土へと還るだけ
それならば一層 斜めを見ずに
おてんとうさんを 仰いでみようか
海を潜るには 息を止めなきゃ潜れない
息を止めるのが いやなら海には入れない
海には海の世界があるし そうして再び 潜らずにいられない
山を又登る 登り疲れてふと休む 辺りの景色が 心支えと又登る
微かに山の匂いを嗅いだ それだけで 人は優しくなれる
波が続く様に 時の刻みも又続く
風も吹き止まぬ 時の刻みも打ち止まぬ
やれこれと返す事のべの中で 何が生きていく 証なんだろか
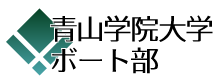



コメント