6月も残り1週間となりました。
こうして日めくり的に数えていけばインカレなんて本当にアッという間にその日がきてしまうのでしょう。
それでもそのインカレに向けては、この先まだ夏の集中練習期間が待ち構えています。
ここが最後の山場となるよう、今年は例年以上の内容を考えていかねばと私が思う反面、そこでどう自分に向き合うかを考えるのも部員らにとって今必要なことなのだと思っています。
例えばこれからのエルゴ測定も一旦はチャレンジ制として、自身が良い感触をもって、記録が出せそうと判断した際にチャレンジすればいいと伝えています。
言わば記録が出ないと思うなら、これを回避し続けることだって出来るわけですが、果たしてそれで本当の勝負ができるか、ということも試されているのです。
特に基準タイムや目標タイムを出せていないなら毎週、毎日のようにチャレンジするくらいの覚悟を決めねば、インカレという高い壁は乗り越えられないのも事実です。
もちろんエルゴがすべてではない、そうは思っていつつも、戦いに挑む上ではこうした気持ちの面はとても重要なことです。
日曜日の午前はエルゴでの練習を予定していましたが、上級生と1年生では取り組む内容がそれぞれ違うため、時間を分けて実施しました。
8時より開始した上級生のメニューは恒例となる5分漕の4セットです。
今までもこなしてきたメニューながら最近では記録も内容も少しマンネリ化してきている印象すらあります。
もちろんこの日は己の気持ち以外にも暑さという天敵が待ち構えていたので、3セット目の一番苦しいセット数の際にはいわゆるバテが顕著に表れてもいました。
そんな彼らの姿を見て、練習後のミーティングである話をしました。
会社や企業でも期初に計画した目標が、なんらかのアクシデントによって悪影響を受け、思うように成績が上がらない場合には下方修正するなり、切り替えることがしばしばあります。
エルゴも自身らが計画したセットごとの距離やLAPがあるわけですが、コンディションによってそれが持続できない状況に陥ったとき、残りの時間や残りのセット数をただこなすだけのものになっている、そう私には映ったからです。
つまり、これでは目標達成におけるプロセスや成長度という本来必要なことを見失い、ただ耐え抜いた安堵の気持ちと頑張ったという自己満足の気持ちだけで終えてしまっているということなのです。
近年の夏の練習でもこのメニューが繰り返されたとき、なんとなく帳尻を合わせて最後に調子を上げていくスタイルが身に付いてきているのもよくない傾向です。
ですから、仮に歯止めが利かずにスコアが落ちたとしても、自分なりの妥協点や目標の再設定をして、それを達成することの方がはるかに意味があることなのだと私は彼らに伝えました。
当然、その日のコンディションや状態は日々異なります。
それでもその中で、自分自身があえて厳しい目標を課してやり終えることと、ただ漕ぎ切った、耐えてメニューをこなしたということでは意味そのものが違うのですから。
そんな精神論のような考え方ですが、セルフコントロールすることがいかに大事かということを今からでも是非知っておいてほしいと思い、この話を述べました。
そして、この5分漕ではあえてレートを指定し、LAPを刻み続けることで、他のメニューにも意味をもつことになるなど、次なる練習への布石になることも示唆しました。
これはあくまで私の感覚ですけど、水中強度って体が覚えるものだと思っています。
その答え合わせがエルゴでもあって、例えばエルゴから遠ざかると、よほど意識して毎日練習に取り組まないと自然と水中強度は落ちてしまうものだと思っています。
もちろん当の本人は一生懸命に漕いでいるつもりなんですが、これが知らず知らずのうちに落ちていくのです。
でもこの水中強度を日々高められる人は競技力をどんどん向上させていけます。
言うならば競技力が高い人というのは常にこの強度を向上し続けられる人なんだと思うのです。
ですからエルゴをするということは水中に噓をつかないで、答え合わせをし続けられることができるのです。
今はスピードコーチという優れものがあります。これにより水上でのスピードを常に意識することができていますが、これも実は錯覚に陥りやすいツールだと結城さんともよく話しています。
私がいう水中強度は体でしか覚えてくれず、仮にスピードコーチばかりに頼りすぎて練習しても結果的に成長していないということは往々にしてあるのだと言うことです。
だから当部の練習では絶妙にエルゴの回数を盛り込んでいます。
これはエルゴ自体を高負荷トレーニングとしているからもありますが、水上での水中強度を再確認する意味も込められています。
エルゴ測定の方が、水上でのレースよりきつく、練習も然りなんてことはざらにありますが、そういう人が多いのも、目に見えない水中強度だと追い込んでいるつもりになっていることが起因しているとすら思っています。
もちろん水を固定できていない、きちんと正しく漕げていないので負荷が分散される、なども理由には挙げられますが、水上で最大限のパフォーマンスを発揮し、維持し続けることがいかに難しいかを知ってほしいのです。
よくよく考えれば私たちの時代にはスピードコーチという物自体は存在していた気がしますが、当然ながら当時の自分たちには手が出るはずもなく、水上での強度の指標はほぼ感覚で練習をしていました。
それでいて、速くなる、強くなるためには、これまで何度も口にしてきたように昨日の自分を超えて、日々積み重ねていくしかないわけです。
でもボート競技とはむしろそういうスポーツであり、そこに挑戦したものが、他競技で日の目を見なかったにも関わらず一躍スター選手として躍り出てくるスポーツでもあるわけですからね。
どんな技術を追求するより、むしろシンプルに考えてほしいと言う気持ちが、この日の私の伝えたことのすべてでした。
また、上級生の練習が終わるとすぐに今度は1年生が集合し、ボディワークを中心にエルゴで30分ばかり漕いでもらいました。
そこは上級生とは真逆の発想で、水中強度より、今は正しい型を身に付けてもらう必要がありますので、当分はこういった基礎練習が多くなっていくことでしょう。
もちろんエルゴの後は炎天下でのランニングや陸トレに移行させ、体力作りも図りつつ、じっくり鍛え上げていっています。
まずはエルゴや水上で高負荷のトレーニングを維持できるための基礎体力も必要なわけですから、焦らず一歩ずつ頑張ってほしいと思います。
この週末は全日本社会人選手権が戸田で行われていたのもあって、そこにたまたま来ていた卒業生の鏑木や、以前指導をしてくれていた元社会人選手が顔を出してくれましたが、現在の部の光景を見て驚いていました。
ほんの数年前は私を含めた3人だけで毎週のようにトレーニングをしていたわけですから、当然のことかもしれません。
でも今はこうして人数がいて、どう練習を組み立てるかなど頭を悩ませながら、徐々に活気付いてきてもいるのです。
そして午後もコース閉鎖を強いられた都合上、エルゴや座学から始め、遅くに開放されたコースで来週のレースに向けた最終確認の乗艇を行いました。
来週はいよいよ新入部員にとっての初めてのレース機会です。
レースを通じて得られるものは多くあります。楽しさであったり、悔しさであったり。
レースに出るからこそ、そこで成果を発揮しようと日々の練習を積み上げていくのです。
そう、ただ積み上げていくだけでなく、自分の目指す先をしっかりと捉えながら努力して、我慢して。
人生もこれと同じです。
人生は我慢することでこそ、拓けるものです。(千里の道も一歩から)
目の前の苦しみから逃げない人だけが遠くに行くことができます。逃げないと決めて我慢して、努力しているうちに道が拓けるものなのです。
なんだか人生観を語ってしまっていますが、ボートは努力が結果に結びつきやすい競技ですからね。
是非、頑張って続けてほしい、そう願っています。
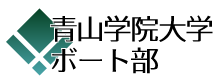



コメント