この時期のボートコースから見る夕日は格別です。
いや、この時期に限らずボートコースからの夕日は何にも代えがたい絶景です。
このコース沿いの道を散歩ルートとしている方は、一目この景色を見ようと国立艇庫前に立ち止まり、スマートフォンを片手に撮影する、そんな様子を幾度となく目にします。
最近は日曜日ともなるとコース閉鎖を強いられ、各大学も午後はフリーにしているところが多いので、コース付近は静かさも兼ね備えています。
だからこそ、この夕日がより格別に見えるのかもしれません。
この日曜日もなんだか先週の繰り返しと言わんばかりの練習内容とスケジュールでしたが、内容だけは大きく違い、収穫や学びもありました。
まず8時集合として先週に引き続きエルゴ5分漕に挑んだ淡路、白川組ですが、先週の指導内容を加味して、4セットとも頑張ればなんとか到達できる目標レベルを設定し、取り組んでくれました。
先週は特に3セット目から大きく崩れ始めて、いわゆるこなすだけの残りセットだったものが、この日はギリギリのところで我慢がきき、安定したLAPを刻み続けることもできていました。
もちろん3セット目を終えた時点で疲労はピークにも達していたでしょうけど、言わば『楽しく、気持ち良く漕げている』ことで、4セット目への気持ちの余裕も随分と違ったように見受けられました。
淡路は最後の最後でわずかに目標に足らずの結果とはなりましたが、それでもこの粘りは久々に見た彼の姿でもあり、それにはっぱをかける白川も先輩に負けじと耐え抜く姿が印象的でした。
4セット目を終えてのいわゆる『ROW OUT』した姿は自分たちでも手応えや成果を感じ取っていることが見て取れ、ここに到達したからこそ次なる選択肢を助言することができました。
その選択肢とは2つです。一つはさらにレートを落としてこの距離、LAPを維持する手法です。
ただ2か月後に大目標を控える二人にとってはさらに高いレートを作りだし、スピード強化を図るほうが必要なことではないかと私は感じましたので、もう一つのさらに高いところで作っていく手法こそベストな選択と思えました。
もともとハイレート体質な長所を兼ね備えている二人であり、体力は十分に持ち合わせています。
それを存分に生かすことを最優先し、ハイレートでトップスピードを磨いていくことこそ、残りの期間で必要なことだと悟り、こちらに挑戦してみようと二人には告げました。
そうです、ここからはメニューも気持ちも『あげあげ大作戦』です!(どこかの監督が言いそうなネーミングですね)
練習の目的を理解し、質を高めることを学び始めた今の彼らであれば思い描くレースプランのために何が必要で、どう取り組んでいくかも理解できるはずです。
私は自分自身がスピード任せにすることを苦手としていたので、あまり好まない手法でしたが、彼らにはそれこそが適していると、ここにきて少し方針を変えていくつもりです。
悔いなく、勝負にかける今夏だからこそ、彼らの持ち味を存分に生かしてやりたい、そう思うのです。
そのエルゴ練習を終えて早々に3人で飯尾と1年生が待つ東京海上艇庫へ移動しました。
この日は全員が測定を予定しており、飯尾はインカレに向けたチャレンジトライアル、1年生は今回は距離を1000mにまで延ばしての測定でした。
飯尾については残念ながら今回も記録更新とはなりませんでしたが、練習後に再確認したところ期限まではチャレンジする意欲があるようですから、今はそっと見守ることにしようと思います。
エルゴこそ記録は止まったままですが、乗艇では成長を見せており、前日の関東理工レガッタでは見事に準優勝を果たしたようです。
着実な成長を確かなものとするためにも残りの期間でなんとか目標達成してほしいものです。
また1年生に関しては前回の500m測定から距離は倍となりましたので、前日の競技の楽しさからは一変し、競技の辛さを体感することになったのではないでしょうか。
その前日ですが、関東理工レガッタに新人ナックルの部で参加し、予選は惜しくもコンマ差の2着で決勝Bに進出。
総合9位という成績でしたが、二本のレースで勝ち負けを体感することができ、ボート競技の第一歩としては良いスタートを切ってくれたわけです。
そして翌日のこの測定ですから、競技の楽しさよりは、むしろ競技の辛い部分を知ることになったわけですが、きっとこれからも練習ではますますこの辛さを知ることになります。
ですが、回りまわって、結果が伴ってくればまたそれが楽しみに変わるのですから、ボート競技を通じて何を得たいか、またどこを目指すのか、これから少しずつ模索していくといいのかもしれません。
もちろん競技の面以外にもかけがえのない仲間と、共に過ごす時間なんかも楽しさの一つなのでしょうからね。
そして、午後は閉鎖を考慮して普段より遅めの17時開始でしたが、懸念していたコース閉鎖はすでに開放されており、待つことなく練習を開始できました。
ただ、この日予定していた付きフォアが想定外のハプニングで使用できなかったため、急遽、1年生クォドと私が乗り込んだダブルとあわせた2艇でスカル種目を体験することになりました。
幸いコースは空いていたので並漕しながら二本オールを体験してもらいますが、予想していた通り、悪戦苦闘の連続でした。
そしてラダーすらまもとに教えていない中での強行を後悔したわけですが、蛇行を正すことを伝えてはいたものの、ついには座礁してしまう結果となってしまったのです。
ですが、失敗から学ぶという意味ではこれをあえて経験させた節も自分の中にはありました。
艇を大事にすること、道具を正しく使用すること、そしていかに安全が大事であるかは、口でいくら伝えても分からないものです。
これを経験することで自分事ととらえ、これから先、自分たちがこの大海原(ではないですが)を出航(出艇)いくにも細心の注意を払うこと、この重要性に気づけるのであれば必要な失敗だとも言えるからです。
この日は技術というよりは、本当に体験に近い練習でしたが、艇を降りる際の注意事項やさらにはクルーが疑心暗鬼になるような行動はどういうものか、など伝えられるだけ伝えたつもりです。
ボートはクルーごとの練習が多いこともあり、小艇など種目によっては自分勝手にという風潮が出やすいのも競技の特性なのかもしれませんが、その自己中心的な考えや行動は組織にとってプラスに働くことはありません。
それは一つひとつの言動も然りです。
親しき中にも礼儀あり。我々は部活であってサークルではありません。
これは決してサークルを否定するような言葉ではなく、部活の定義とは「活動を通じて成果を残すこと」と言われているからです。(サークルの定義は趣味や交流を楽しみ、自由な雰囲気で活動することと言われています)
だからこそ個人としても、組織としてもルールや秩序を保ちながら、皆で成果を出していくための心がけが必要なのです。
私は失敗した彼らを責めることは基本的にしません。但し、一度伝えたことを守らないことや、風紀が乱れることには練習以外のことでも厳しく言うつもりです。
常に言うように我々の判断基準はそれが「部にとって良いことか、勝つための行動か」、ここに拘ってほしいからです。
それは今も昔も変わらない私たちの価値になります。
多くの新入部員を迎え入れ、皆の気持ちもモチベーションも、そして戦績もこれからは上がる一方でしょう。
だからこそ、ここから良い組織を皆で作っていってほしいと思います。
インカレに向けてだけでなく、部としても『あげあげ』となるよう、大作戦の名のもとに。
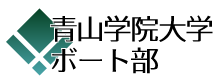



コメント