インカレが終わり、今は長期オフ期間。
部員たちはそれぞれ、つかの間の休息を楽しんでいることでしょう。
私自身もこの機会に実家へ帰省し、心身ともにリフレッシュしたいと思っています。
次なる目標は新人戦。
そのためにも、今はしっかりと英気を養う時間が必要です。
もはや伝統文化のような最終日の光景
インカレ最終日、大トリとなる男子エイトの決勝レース後には部員、OB・OGそして保護者の皆さんに声をかけ、国立艇庫前に集合していただきました。
前回ブログでも触れたように、この日は、一部の部員らがレースに出場していたこともあり、大会期間中で最も多くの応援者が駆けつけてくれました。
インカレ最終日をご覧になった方はご存じかと思いますが、その日だけは戸田も普段では考えられないほどの賑わい。
どこからこんなに人が集まったのかと思うほどの光景は、もはや“伝統文化”のようでもあります。
そんな中、当部の関係者で集まり、大会における締めと集合写真を撮り、最後は主将・淡路の胴上げを行いました。
4年間の労いと、これからの門出を祝う意味を込めて。
初めて担ぎ上げた淡路は、やたらと重く感じました(笑)。
そんな主将の重みを、来季は新主将・飯尾が受け継ぐことになります。
主将選出の葛藤と、チームの判断基準
今回の主将選出には、正直なところ大いに迷いました。
もう一人の候補・白川も含め、どちらにも長所と短所があり、誰がチームを引っ張るべきか、コーチ陣・前主将・当人たちを交えて、長く話し合いを重ねました。
最終的には、飯尾が自ら手を挙げたこと、その意欲に敬意を表して決定しました。
ただし、主将は単なる“インカレ後の代替わり”ではなく、チームに大きな影響を与える存在です。
最上級生であるかどうかに関係なく、今後も必要に応じて体制の見直しや議論を行っていくつもりです。
その根底にあるのは、常に「チームが良くなるために」という視点。
これは、昨年のインカレ後のミーティングでも皆に伝えた、一つの判断基準です。
「チームが良くなるための行動か」
「チームが勝つための行動か」
※ここで言う“勝つ”とは、目標を成し遂げることを指します。
これが今のボート部で優先すべき判断基準です。
個人の目標や思いは尊重しつつも、チームとしてどうあるべきかを導くのが、私たち指導者の役割だと考えています。
主将という存在は、現場で我々以上にそれを浸透させていく役目を担ってもらわねばなりません。
この先、部員が増えれば、意見の食い違いや軋轢も生まれるでしょう。
だからこそ、立ち返るべき判断基準が必要なのです。
当初、飯尾に主将としての目標を聞いたときには、正直、疑問と違和感もありました。
しかし、話し合いを重ねる中で、彼自身がチームの目標や判断基準を理解し、言葉にしてくれたことが決め手となりました。
飯尾に託した今は、彼を信じて、育てていこうという思いです。
前回の投稿では「経験が人を育てる」と書きましたが、今回はまさに「立場が人をつくる」。
その成長に期待しています。
ミーティングと打ち上げ、それから
今年もインカレ後、合宿所で全体ミーティングを行いました。
この夏は離れて活動することが多かったため、全員が顔を揃えるのは久しぶり。
それぞれが過ごした夏を振り返り、これからに向けての確認を行い、一区切りをつけました。
休みを挟んで、どんな気持ちでまた集まってくれるのか。
不安と期待が入り混じるのが本音です。
そして、恒例の打ち上げ。
今年からは保護者の皆さまにもご参加いただき、盛大に開催しました。
その場で、淡路は引退の挨拶とともに、部員一人ひとりにメッセージを贈ってくれました。
そんな淡路から私に贈られた言葉に、私は胸がじーんと熱くなったのですが、その中に「結果で恩返しができず申し訳ない」という言葉もありました。
でも、当日は時間の都合もあり、伝えきれなかったことがあるので、ここで改めて綴らせてください。
「勝って恩返し」なんて、思わなくていい
まず、今回のレースに出場してくれた選手たち、支えてくれた部員たち、そして応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました。
結果として、掲げた目標を達成することはできませんでした。
それを導けなかったことは、指導者として申し訳なく思っています。
ペアのレース後のミーティングでは、感情を抑えきれず、お見苦しい姿を見せてしまいました。
年々、「勝たせてやりたい」という思いが強くなり、気持ちばかりが先行していた一年だったと、今は振り返っています。
特に淡路には、この4年間、本当に多くのことを求めました。
それに応えようと、彼は必死に頑張ってくれました。
だから今は、ただただ感謝しかありません。
試合後の夜、淡路から「勝って恩返しできず申し訳ない」というメッセージが来ました。
でも私は、あえて返信をしませんでした。
それは、この打ち上げの場で直接伝えたかったからです。
「勝って恩返し」なんて、思わなくていい。
「期待に応えられなかった」なんて、思う必要はないのです。
我が子がどんなに問題児でも、思い通りにならなくても、どうにかしてやりたいと思うのが親心です。
保護者の皆さんも、結果ではなく、頑張る姿を見たいから応援に来てくださっているのだと思います。
中には勝手に期待をかけて、結果に失望する親や指導者もいるかもしれませんが、子や選手が、自分の期待通りに、自分の思い通りになど、なるはずがないのですから。
結城コーチが、我が子の決勝レースを前に自分事のように緊張して、吐き気を堪えていた姿を見て、「これが親の姿なんだな」と、私はむしろ羨ましくも思いました。
ただ私も、部員たちをいつも同じような気持ちで見ています。
実力うんぬんではなく、関わった一人ひとりを、ずっとそう見てきました。皆、一生懸命にひたむきに頑張ってくれるからです。
夢を託す理由
外向けには「日本一を目指す」なんて大それたことを言っていますが、これは私自身の人生の夢でもあります。
でも、部員たちにはただ、ボート部で過ごす時間が有意義であってほしい。
努力、勝敗、仲間との時間──すべてが糧となって、巣立っていってほしい。
それは、誰かのためではなく、自分の人生のために。
私たちは、それを応援するだけです。そういった親心をもって指導を続けているのです。
もちろん選手たちが、一生懸命に努力し、成長し、勝つ。
それは本当に素晴らしいことですし、だからこそ、そういう景色も見せてやりたい。
それが、私の指導の根幹にある思いでもあります。
今年は特に、自分の指導にも限界を感じました。
だからこそ、公認コーチ3の研修に挑戦し、新たなコーチの招聘も進めています。
毎年思います。
「来年こそは」と。
そしてその思いは、年々強くなっています。
今度こそ、悔し涙ではなく、嬉し涙を流したい。
それが本音です。
そんな思いを、勝手に部員たちに背負わせてしまっているかもしれません。
でも、青学ボート部の部員たちには、それを託すだけの価値があると信じています。
そして、いつの日か。
卒業した部員たちや、支えてくれる皆さんと一緒に、その景色を見たいのです。
ボート競技が嫌いだった私が、今ではこの環境なしでは生きていけないほどになっています。
でも、この競技があったから、皆に出会えた。
さまざまな感情を分け与えてもらえた。
だから、心から感謝しています。
ここに関わるすべての方へ。
これからも、共に歩んでいきましょう。
2025年9月13日 青山学院大学ボート部 監督 須田 祐樹
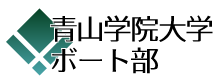



コメント