火曜日の投稿が日課になっていたものの、先週は忙しさにかまけて更新できず、土曜日の投稿となってしまいました。今週はようやくいつものペースに戻っただけですが、それでも日々休みなく働き続けるのはさすがに無理があるようで、先週末の日曜日は久々にゆっくり(?)起床することができました。
とはいえ、土曜に続いて日曜も冷たい雨の中での練習。カッパに長靴という完全防備で参加し、元さんとともに自転車伴走で各クルーに指導を行いました。
この日は花岡が不在でしたが、ダブルスカル2艇にシングルスカル1艇が出艇。今後さらに2艇ほど増える予定で、すべてのクルーに並走するのは現実的に難しくなってきます。
かつては2クルーが基本だったことを思えば、指導者が増えた今の環境は本当にありがたい限りです。
私はもともと陸から声を上げてアドバイスするのが得意ではないのですが、ビッグメガホンを背負い、漕ぎながら常に声をかける元さんの姿に触発され、私もできるだけ声をかけるようにしています。らしくない自分に少し恥ずかしさも覚えつつ、それでも今は初期段階のクルーが中心なので、一つひとつの声掛けが大きな改善につながることを実感しています。
何より、わずか2カ月弱でこの環境に慣れ、積極的に指導してくれる元さんからは、学ぶことが本当に多いです。技術的なアドバイスはもちろん、指導者としての姿勢にも刺激を受けています。
特に印象的だったのは、この日、徳谷・髙橋ダブルが練習後に岸に艇をつけた際、目を離した隙に転覆してしまった場面。元さんは冷静かつ的確に対応し、まずは冷え切った体を優先して合宿所へ戻るよう指示。その後、艇庫に戻って転覆の経緯や技術の振り返りを行う姿勢には、深く感心しました。
私も現在、JARAのコーチ3研修を受講中で、技術面や指導者としての考え方を体系的に学んでいます。元さんはすでに資格を取得されており、これまで多くの大学で指導されてきた経験から、日々の指導が自然体で行われていますが、これは誰にでもできることではありません。
特に経験者が多い大学では、直接的な指導や管理が少ない傾向にある(私見ですが)中で、ここまで基礎から丁寧にレクチャーしてくれる姿勢は、学生たちの経験の差を埋めるための大きな力になっていると感じます。
むしろ高校経験者なんかは、細かな技術を教えられるより、なんとなく自然と漕げるようになる選手の方が多かったりするのでは?と思うこともありますが、こうした基礎的な考え方をしっかりと教えてもらえる機会はボート界では貴重だと思うのです。
コーチ3研修では、ボートの基礎・応用、指導者としての心構えなど幅広く学べますが、こうした研修をどれだけの指導者が受講しているかは定かではなく、指導者による個人差は大きいと感じます。
メジャースポーツでは、研修制度やメディアを通じて指導者の考えに触れる機会がありますが、ボート界ではそうした機会は限られています。公認コーチ制度が唯一の取り組みであり、それも個人の意思に委ねられているのが現状です。
大学連盟が立ち上がり、選手育成に向けた検討機会が設けられていることは心強いですが、指導者の学びの場ももっと必要だと感じます。
もちろん、ボート競技の指導者はボランティアが主であるため、どこまで自発的に取り組めるかには課題もあります。それでも、一監督として、一指導者として、何ができるかを考え、こうしてブログで思いを綴ることで、一石を投じたいという気持ちがあります。
すべては選手たちのため。そして、ボート界全体が発展し、ニュースターや著名な選手が生まれることを願っています。
その中に、私たちの教えを受けた部員たちが、さまざまなステージで活躍してくれることも含まれているのです。
だからこそ、日々の指導や成長できる環境づくりは我々の使命であり、何より選手たちがボートを好きになり、高いモチベーションで取り組んでくれることが一番の喜びです。
休みがなくても、朝が早くても、指導者としてこの場にいられることは、私自身の喜びでもあります。
直接話したことはありませんが、きっと元さんも同じ思いでいるのではないかと、コース上で指導する姿を見て感じています。
そして、部員たちに注がれる愛情という意味では、結城さんも亮太も自己犠牲を厭わない頼れる存在。常に感謝の気持ちを持って向き合っています。
監督という肩書きで何ができるかというより、私はスタッフや部員たちの架け橋、ハブのような存在でありたいと思っています。案外、こういう存在は重宝されるもので、監督業以外でもその利点を活かしているのかもしれませんけど。
さて、また指導者論をつらつらと語ってしまいましたが、今日の本題はそこではありません(笑)
この日は8時からの練習で、体が空いたのは11時半過ぎ。一度帰宅し、あまり休む間もなく14時からは八木さんによるヨガレッスンを行ってもらいました。
これまでもヨガについて練習の一環で取り組んでもらってきましたが、「なんとなくやらされているのでは?」という疑問もあり、この日は目的をしっかり伝えたいと思い、その場に参加し、話をしました。
ちなみに。まずヨガには以下のような効果があります:
- 柔軟性の向上
- 体幹の安定性とバランス力の強化
- 呼吸法による集中力と持久力の向上
- リカバリーと疲労回復
- メンタルケアとストレス軽減
これらはボート競技とも非常に関連性が高いですが、私が今もっとも皆に着目してほしいのは「パワーポジション」についてです。そのことをこの日は伝えたのです。
世界と日本の差を写真で見比べながら、私なりの持論を述べました。
パワーポジションとは、最大効率で力を伝えられる身体の配置のこと。
具体的には:
– 骨盤が立ち、体幹が安定している
– 股関節がしっかり屈曲し、膝と足首が連動している
– 背中が丸まらず、胸が開いている
– 肩甲骨が安定し、腕がリラックスしている
この姿勢は、キャッチからドライブにかけての力の伝達効率を最大化し、怪我の予防にもつながります。
当部がヨガを取り入れている目的は、選手が自分の身体の使い方を理解し、最適なパワーポジションを習得することにあります。
これは練習量だけでは補えない「プラスアルファ」の要素です。
絶対的な力差はフィジカルに依存しますが、それを引き上げるためにも、全員がこのプラスアルファを取り入れることで、より少ない練習でも競技者としての質を高めることができると考えています。
元さんの技術指導、神楽坂でのフィジカルトレーニング、そしてヨガ。これらをどう取り入れていくかで、選手たちは大きく成長してくれるはずです。
すべてを正しいと思わなくても構いません。でも、こうしたきっかけを与えることが、今の我々の務めです。
強豪大学では、選手が自ら考え、教え合い、技術もフィジカルも高めているそうです。当部はまだそのような環境にはありませんが、それこそが今の「ウリ」でもあると思っています。
私自身、これまでの指導歴で良いと思ったことは常に取り入れてきました。この姿勢はこれからも変わりません。
青山学院大学ボート部として、日々新しいことにチャレンジし、進化していくために、ぜひ皆も一緒になって考えていきましょう。
(今回も持論全開の内容になってしまいましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました!笑)
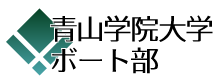



コメント