皆さん、大変です。
今週の天気予報では最高気温40度という表記が話題になっていました。
蓋を開けてみれば今日の埼玉の最高気温は39度のようですが、もはや外で過ごすのさえも危険なレベルで、記事にも出ているようにこれは災害級の暑さです。
ボート部でもいよいよ先週末より〝夏練2025〟が開始となりましたが、暑さを考慮し、時間帯を見て活動をしていくこと、また水分をしっかりとりながら、体調が悪い場合は無理をしないことが必要です。
特に平日の現場には学生のみしかいないわけですから、万が一に備えた連絡体制なんかも整備しておかねばと昨日、全体LINEで発信しました。
この異常な暑さがあってというわけではないですが、私の出勤はいつも早いので職場に着いた頃には汗だくで、、、というのは実はあまりありません。(早起きは三文の徳?)
それでもこの早い時間に最寄り駅を降りると数人の学生らがラクロスのスティック?をもって毎朝、河川敷を目指しているのを目にします。
恐らく近くにラクロスの練習場があるのでしょうけど、練習着に書かれた大学名は毎日違うので、多くの大学のラクロス部員が集まる聖地がきっとこの近くにあるのでしょう。
本学の部活動でもやはりラクロスは盛んに活動されています。
大学から始められる点はボート競技とも似ていますが、あちらはどちらかと言うと華やかさがあるようで、ラクロス志望の学生に振られることはいつの時代も同じでした。
でもこうして早朝から、はるばる遠い練習場へ通っているのを見れば同じ大学の部活動でありながらなんの差があるのだろう?と疑問にも思うのです。
今年こそ当部も多くの新入生を迎え入れましたが、いつの日かボート部も華やかな大学スポーツの憧れの場としてラクロス部のように数十人の入部希望が来る日もくるのでしょうかね。
さて、そんな叶わぬ夢は置いておいて、我らがボート部も今年は選手総勢9名で夏練に突入しました。
当初は9名もいるとどういったかたちで練習をしていくかに頭を悩ませてもいたのですが、間際になって嬉しいお誘いをいくつかいただき、結果的には4つの編成に分かれてこの夏を過ごすことになりました。
むしろ当部の練習として私が決めた練習をこなすのはインカレを目指すペアの二人のみで、その他は他大学との混成エイトを目指し、取り組んでいくことになりました。
1つ目はインカレへの道が途絶えた飯尾ですが、こちらは千葉大学、海洋大学との混成エイトに声をかけていただいたようで、オッ盾レガッタを目指すします。
これはインカレに出場できない上級生や1年生が入り混じったMIXクルーのようですが、恐らく飯尾が最上級生でもあるでしょうからリーダーシップにも期待されているのでしょう。
飯尾自身も一年次は同様に他大学との混成エイトで夏を過ごしました。
その時には他大学の上級生が同じく参加をしてくれ、その背中を見てきたわけですから、この機会を通じてまた一段と成長してくれることを期待しています。
そして次なる混成は成城大学さんを主体とした女子混成エイトに重信菜名ちゃんが参加します。
こちらは成城大学、学習院大学、共立女子大学と本学の4大学が集うエイトで、ジャパンオープンレガッタへの出漕を予定しています。
上級生も数名乗る混成ですが、経験年数はともに浅いようですから、皆、同じような境遇の集団エイトになりそうです。
特に戸田の艇庫を構える大学とのコラボということもあって、午前の練習はなんと早朝5時集合。
これはそれこそラクロスにはないであろう戸田ならではの時間帯であり、いきなりのこの時間設定に戸惑うのでは?と不安視したものの菜名ちゃんは快く了解をしてくれ、参加しています。
当部では久々の女子漕手ですからここでの機会に基礎を学んでもらい、秋の新人戦につなげ、かつ、他大学との交流が今後も広がっていければと期待します。
そして最後の混成は立教大学さんからお誘いをいただいた混成エイトです。
戸田にある同じミッション系の大学で、十字ブレードも同じでありながら、これまであまりこうした機会を持てずにいましたが、今回、ありがたいことにお誘いをいただき、こちらもオッ盾レガッタへの参加を予定しています。
但し、5名の男子漕手の中からレースに出場できる正規メンバーは2名。
そう、今回は当部の中でもシートレースが繰り広げられ、上位2名のみが参加することになるのです。
部員が増えてくれば今後もこのようなシートレースという機会は当然増えますし、同級生でも互いに切磋琢磨し、刺激し合うことは大いに必要なことです。
またこのエイトには半分は上級生が乗る予定のようなので、単に参加を目的としているだけではない一つ上の恵まれた境遇でもあるのだと思います。
そして、同じく未経験の一般学生からでもインカレ上位を賑わす強豪校ですから、一つでも多くのことを学び、部に還元してくれればと期待しています。
こうした他大学との交流機会も戸田、ボート界ならではのものであり、特に夏のこの時期であればこうして一緒に活動ができるのも素晴らしいことです。
もちろん自分たちが目指すべき部の姿、選手としてのパフォーマンス、これはこの先の活動でそれぞれ見えてくるものかもしれませんが、外の環境を見て、知ることでこそ多くの学びを得られます。
そして先々は良いライバル関係ともなり、やがては社会に出てからも繋がっていられる良い関係性となっていけば嬉しくもありますからね。
またこんな機会だからこそ、青山学院大学ボート部の部員であることの誇りを胸に、またその名に恥じぬよう、挨拶含めた行動をしっかりとして、良い影響を与える存在であってほしいと私は願っています。
挨拶はするしないだけではなく、されるようになることも本当に重要です。
挨拶をしない奴、なんて大の大人が愚痴や文句のように口にすることも多々ありますが、されない自分についても考えるべきだと私はいつも説いています。
もちろん自分から進んですることは大いに奨励していますが、嘆くばかりでなく、その必要性を説き、挨拶をされるよう自らも変わっていかなければという戒めも込めています。
今年の1年生には特にこの挨拶について何度か口にもしてきました。
そう考えると近年はそれを口にしなくてもしっかりと挨拶ができる部員や環境が当たり前に定着していたのかもしれませんが、挨拶を自ら進んでできることこそ、当部の部員の象徴でもあってほしいのです。
それは相手を知る知らないに関係なく、このボートコースや艇庫の関係者にも自ら進んで行うことで青山学院大学ボート部を宣伝することになるのですから。
たとえ強豪でなくとも構いません。こうした行動一つ一つの積み重ねで青学らしさを築いていってくれることを一番に願っていますので、皆で共に成長していきましょう!
それでは最後に挨拶の格言、名言を参考までに。
- 「挨拶は心の窓を開く鍵である」
― 人との関係を築く第一歩として、心を開く行為であることを示しています。 - 「良い挨拶は、良い一日をつくる」
― 朝の一言がその日の雰囲気を左右することを表しています。 - 「挨拶は相手への敬意の表れである」
― 礼儀としての意味だけでなく、相手を尊重する姿勢を示すものです。 - 「笑顔の挨拶は、言葉以上の力を持つ」
― 非言語的なコミュニケーションの力を強調しています。 - 「挨拶は人間関係の潤滑油」
― 組織やチームの円滑な運営に欠かせない要素としての挨拶の役割を表現しています。
なぜ必要かを理解した人はこれまで以上の挨拶を心がけてみてください。それはきっと今の自分を変える機会にもなるはずですから。
そしてその一言がその場の空気を変えることもあるのです。さぁ、早速今日から行ってみてはどうですか?青山学院大学ボート部の代表として。
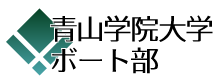



コメント