さて、お盆休みと言われる連休が過ぎ去りました。
休み明けに加えて、暑さが一段と増すこの時期は、心身のコンディションを保つのも一苦労です。
ボート部はというと、世間の盆休みなど関係なく、日々練習に明け暮れています。
私自身も週末に一度も顔を出せないと、ものすごく長い時間が空いたような感覚に陥ります。
ですから先週はまさにその状態で、いてもたってもいられない気持ちでした。
土曜日は勤務上、一日仕事でしたが、練習終わりにでも顔を出せないかと仕事を早めに切り上げ、なんとかコースに辿り着いた時、ペアの二人がまだ水上にいるのを見てホッとしました。
週中はTAから送られてくる動画だけが頼りで、その動画で動きは常にチェックしていますが、やはり実際の艇上でのスピード感や空気感は、現場でしか感じ取れないものがあります。
直接目にするのに長く空いた期間に不安もありましたが、少なくとも変化が見られたことは収穫でした。
二人が私の存在に気づき、「どうですか?」と声をかけてくれた時、週中に結城さんからもらったアドバイスを意識している様子も見られ、リズムやセットが以前より良くなっていることを伝えました。
ただ、課題としているキャッチについては、二人ともまだ試行錯誤している様子があり、残り時間でどれだけ成長できるかが鍵になります。
そんな二人を尻目に、この日初めてペアに乗ったと言う飯尾が横を通り過ぎていくのを見て、その動きには驚かされました。
ブレードワークが非常に自然で、理想的な動きをしているのです。これは、今年一年間シングルスカルで積み重ねてきた成果の表れなのでしょう。
そしてこの日は練習後には淡路、白川を誘って高級焼肉を堪能しました。(全員連れていけないのは申し訳ないところです)
これは労いの意味もありましたが、実際にはコミュニケーションの場としての意味合いが強かったかもしれません。
こうした何気ない時間も、部活動においては大切な要素です。とはいえ、部員数が増えてくると、時間も費用も限られてくるのが悩ましいところです(笑)。
それでも日頃の頑張りのご褒美も時には必要なので、また折を見て、メンバーを変えてこうした機会も意識的に作っていこうと思います。
そして翌日は恒例のエルゴメニュー。混成エイトから漏れた仲村、花岡、松江の1年生3名もここに加わりました。
ただし、ペアの二人とは別メニューで30分エルゴを行うことになり、久しぶりにその姿を見る機会ともなりました。
ペアの二人に至っては暑さの影響もあってか、スコアが伸び悩んでいる様子でしたが、ここまで来ると自分自身で自分を追い込むしかありません。
この一本一本の積み重ねが、レースでの結果に直結します。
ボート競技は、苦しいときにいかに自ら耐え、相手を競り落とすかの勝負です。耐えなければ負けるというシンプルそのものですが、だからこそこうした日々の練習が重要なのです。
後悔は先に立たず、いつもレース後に感じるものです。そのレースでいかに勝ち切れるか、このイメージをしっかり持って取り組んでいってもらいたいものですね。
一方、30分エルゴに取り組む一年生の姿には、目的意識や改善への意欲があまり感じられず、後方から私がこっそり撮影した動画を見た亮太コーチからは「地獄絵図のようですね」とコメントすらありました。
苦しそうに見えるのは、単に体力的な問題だけではなく、動機の質にも関係しているのかもしれません。
自己決定理論では、動機は大きく「内発的動機」と「外発的動機」に分けられます。
外発的動機:誰かに言われたから、怒られたくないから、評価されたいから。
内発的動機:自分が成長したい、達成感を得たい、挑戦したいという純粋な欲求。
練習だからやる、先輩に言われたからやる、というのはどちらかと言うと外発的動機です。それでは、苦しい練習に意味を見出すことは難しく、継続も困難です。
一方で、「インカレに出たい」「勝ちたい」「自分の記録を更新したい」「成長したい」といった自己実現への欲求は、内発的動機に基づくものです。
この内発的動機こそが、苦しい練習を乗り越える力となり、競技者としての成長を支える原動力になります。
そして練習の一つ一つにも必ず意味があります。
動的ストレッチ、静的ストレッチ、フィジカルトレーニング、ヨガ、テクニカルドリル…すべてが目的に向かうための手段です。
その意味を理解し、主体的に取り組むことこそが、大学スポーツの本質であり、部活動の価値でもあるのです。
この日の動画を私はあえて後方からの動画のみを共有しました。
何度か真横からの撮影も試みたのですが、それは私が撮影しているときだけ意識をして漕いでいるように見えたので、そこにあまり意味を見出せずにもいたからです。
見られているから漕ぎや姿勢を正すではなく、見られていないときにこそ意識して、継続し続けることが本当の意味で価値があるということを知ってほしくもあったからです。
この後方からの動画を見た自分たちの姿は果たしてどう映ったことでしょうか。
誰かに言われたからではなく、『自発的に、主体的に』がこのボート部での活動の根底にもあるわけですから、我々がその大切さや意味を今一度言い続けていくしかありません。
そして上級生らもそういうことを当たり前にしていってほしいなとも感じています。
今、混成エイトで他大学にお世話になっているメンバーは、他大学の教育体制や取り組み方の違いを肌で感じていることでしょう。
我々は少数でやってきたがゆえに、こうした仕組みやシステムが定着していません。それは私自身の責任でもありますが、部員たちの意識改革も必要です。
『自発的に、主体的に』
それは、内発的動機で集う部活動だからこそ、当たり前にしていかなければならないことなのです。
自分を高めることに注力するあまり、組織としての活動や取り組みが疎かになりがちですが、部員数が増えた今こそ、仕組みやシステムを構築していく必要があります。
これからは皆で一緒に、意見を出し合い、どう変えていくか。自分たちで作っていける楽しさも、この部活動の魅力の一つです。
インカレまであと2週間。
勝負の時はもうすぐですが、この夏、また一つ部が成長していくことを期待しています。
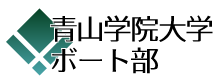



コメント